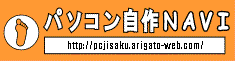ペルチェ素子
熱エネルギーと電気エネルギーが相互に変換する現象を熱電効果といいます。 ペルチェ効果は、熱電効果の一種です。
ペルチェ効果とは、異種の導体の接触面を通じて電流を流したとき、その接触面で熱量の発熱または吸熱が起きる現象のことです。 ペルチェ効果には、電流の向きを変えると発熱、吸熱が逆転するという性質があります。
このペルチェ効果を利用して冷却効果を生み出す、薄い板状の電子部品がペルチェ素子です。 ペルチェ素子に電流を流すと、ペルチェ効果によってその両側に温度差が発生するしくみになっています。 ただし、ペルチェ素子そのものは、あくまで温度差を作るだけのもので、冷却能力は持っていません。
ペルチェ素子による冷却の原理は、次の通りです。 まず、ペルチェ素子によって温度差を作ります。 そして、冷却する側とは反対側を冷却することにより、冷却する側の温度を下げます。
例えば、冷却する側が80度であるとし、ペルチェ素子によって50度の温度差を発生させたとします。 このとき、冷却する側の反対側は130度です。 それを100度まで下げれば、冷却する側が50度まで下がります。
それでは、ペルチェ素子によってなぜ冷却効果が得られるかというと、 例えば、周囲の温度が25度であれば、50度のものを30度にするより、 100度のものを80度に落とすほうが簡単だという性質に基づいています。
そして原理的には、ペルチェ素子に流す電流の量を増やすことによって強制的に温度差を広げることができ、 その結果として冷却効果を高められるところが、この冷却方法の強みなのです。
しかしながら、ペルチェ素子を利用したCPUの冷却を行うときの注意点がいくつかあります。
- ペルチェ素子の温度差を大きくするほど、消費電力が飛躍的に増加します。 電源容量が追いつかないといった実用上の冷却能力の限界が存在します。
- CPUの発熱量が増えると、ペルチェ素子の温度がとても高くなるため、 それを冷却できる強力な装置が必要になります。
- 冷却対象となるCPUの熱量とクーラーから発生する熱量をあわせた分の熱がPCケース内に滞留します。 したがって、PCケースの放熱対策が必要になります。
- ペルチェ素子を利用したCPUクーラーは結露が発生します。 結露対策を怠ると、CPUやマザーボードにダメージを与える危険性があります。
以上のことから、ペルチェ素子による冷却方法は、コスト面で判断するとあまりよい方法ではありません。
実際、ペルチェ素子によるCPUの冷却は、主にオーバークロック目的で使われています。